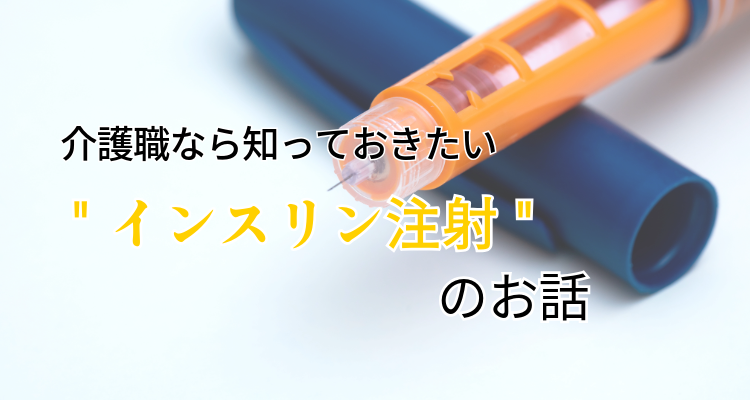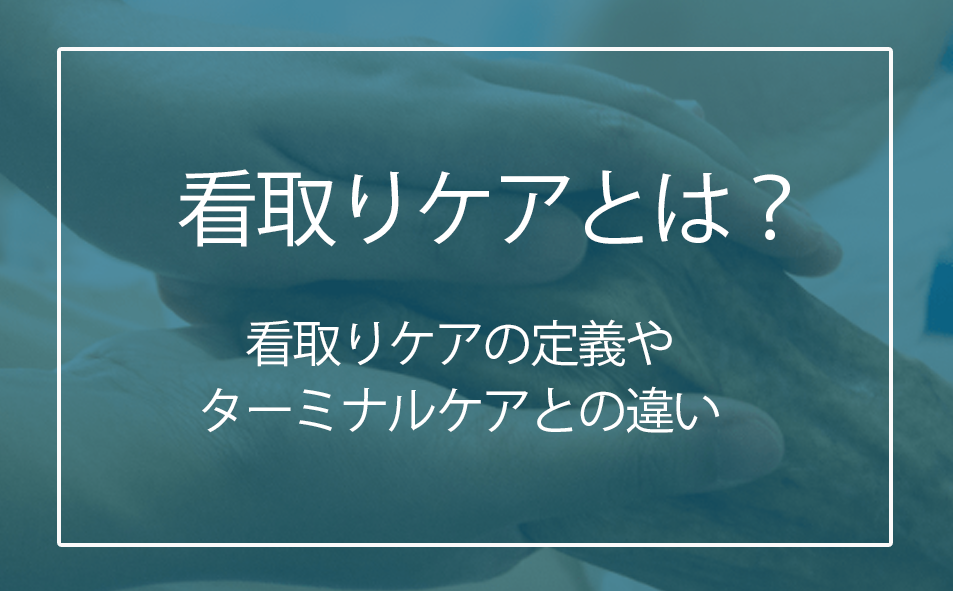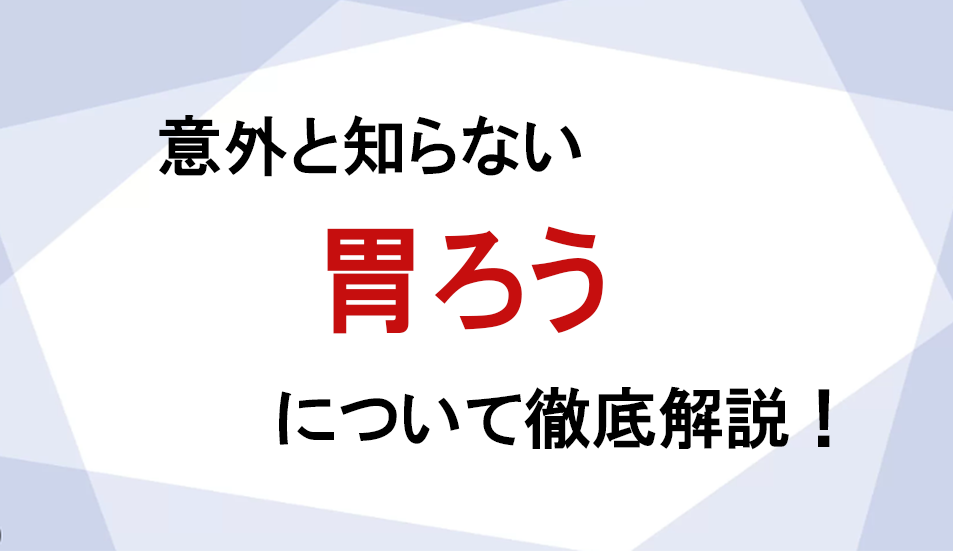認定調査で失敗しない!押さえておきたいポイントと準備
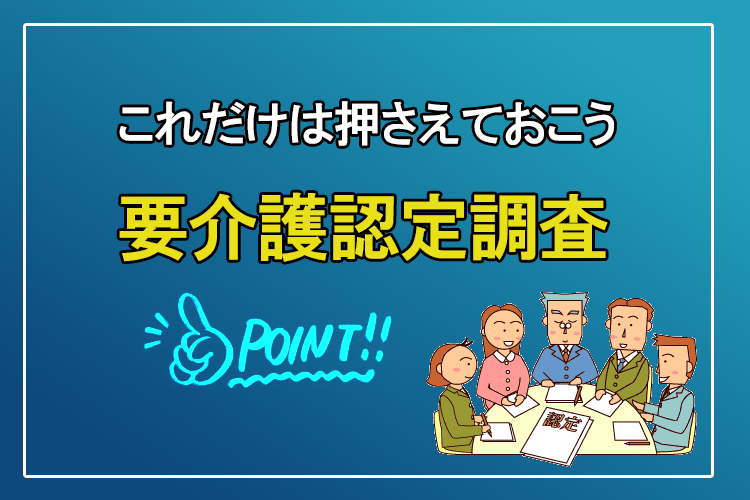
調査員の前で “できるふり” をしていませんか?
要介護認定調査は、今後の生活を大きく左右する「運命の30~60分」です。
実はこの調査、
「きちんと準備をした人」と「準備ゼロの人」では、
結果がまったく変わってしまう可能性があります。
たとえば…
- 本当は歩くのがつらいのに、つい無理して見せてしまう
- 家族が代わりに答えすぎて、本人の困りごとが伝わらない
- 調査員に何を聞かれるのか分からず、不安のまま当日を迎える
- 認知症の症状がうまく説明できず、本来受けられるサービスが減ってしまう
これらは、実際の現場でとても多く起きている“認定調査の落とし穴”です。
しかし…
安心してください。
認定調査は「コツ」を押さえるだけで、必要な支援につながりやすくなります。
逆に、準備なく受けてしまうと、本来利用できたはずのサービスが受けられず、
後から「こんなはずじゃなかった…」と困ってしまうことも珍しくありません。
今回の記事では、
- 調査の仕組み
- 事前準備で“絶対に押さえたい3つのポイント”
- 当日にやってはいけないNG行動
- 結果に納得いかないときの対処法
など、失敗しないための実践的なノウハウを、できるだけわかりやすく解説していきます。
「認定調査って難しそう…」
「調査員の前でどう振る舞えばいいの?」
そんな不安を感じている方でも、この記事を読み終えるころには、
“落ち着いて調査に臨める自信” がきっと持てるはずです。
それでは、まずは「要介護認定調査とは何か?」から見ていきましょう。
◆ 要介護認定調査とは?
調査の目的と全体の流れ
介護サービスを利用するには、まず「要介護認定」を受ける必要があります。これは、あなたがどれくらい介護を必要としているのかを客観的に判断し、その人に合ったサービスにつなげるための最初のステップです。
要介護認定の目的は、「本当に必要な人に、必要な介護を公平に届けること」。
高齢化が進む今、介護が必要な方は増えているため、限られたサービスを適切に届ける仕組みがとても大切になってきています。
認定調査では、調査員がご自宅や施設に伺い、心身の状態や普段の生活の様子についてお話を聞いたり、実際に動作を見たりして、状態を確認します。その情報は、医師の意見書と合わせて「介護認定審査会」で審査されます。
最終的な認定結果は、
要支援1・2
要介護1~5
の 7つの区分 のいずれかとして通知されます。
この区分によって、利用できるサービスの内容や量が変わるため、とても重要なプロセスになります。
ケアマネジャーはこの結果をもとに、あなたに合ったケアプラン(サービス利用計画)を作り、必要なサービスへとつなげていきます。
つまり、認定調査は介護サービスの入口であり、人生に関わる大切な場面。そのため、調査に向けての準備や正確な情報共有がとても重要になります。
◆ 要介護認定の流れ
認定結果が出るまでには、いくつかのステップがあります。ざっくり説明すると次のような流れです。
- 市区町村の窓口で申請
本人でも家族でも申請できます。 - 調査員が訪問して聞き取り・観察調査
心身の状態、暮らしぶり、できること・難しいことなどを確認します。 - 医師が「意見書」を作成
医学的な視点からみた状況をまとめ、認定に必要な情報となります。 - 介護認定審査会で総合判定
専門家が、訪問調査の結果と医師の意見書をもとに要介護度を判定。 - 結果の通知
要支援1~2、要介護1~5のいずれかが決まります。 - ケアマネがケアプランを作成してサービス利用へ
必要に応じてサービスの調整が始まります。
もし結果に納得がいかない場合は、「不服申し立て」も可能です。
ただし期限がありますので、早めの対応が必要です。
◆ 認定区分と利用できるサービス
要介護認定の結果は、「要支援1・2」から「要介護1~5」まで、全部で7段階に分かれています。どの区分になるかによって、利用できるサービスの内容や上限額が変わります。
● 要支援1・2
比較的自立度が高く、生活の中で一部サポートが必要な方向けです。
利用できるのは主に 介護予防サービス で、例えばこのようなものがあります。
- 生活援助中心の訪問介護
- デイサービス(通所介護)
- 福祉用具の貸与 など
目的は「今の生活機能を維持・向上させること」。
“できることを増やし、介護が必要な状態をできるだけ遅らせる” ことを目指します。
● 要介護1~5
日常生活で介助が必要な方が対象になります。
要介護度が高くなるほど、利用できるサービスの範囲も広がり、上限額も大きくなります。
利用できるサービスの例としては、
- 身体介護・生活援助の訪問介護
- デイサービス
- 訪問入浴
- 福祉用具購入・住宅改修
- 特別養護老人ホームなどへの入所
などが挙げられます。
必要なサービスは人によって大きく異なりますので、ケアマネジャーと相談しながら、生活に合ったケアプランを作成していきます。また、時間とともに状態が変わることもあるため、状況に応じて「区分変更申請」も可能です。
◆ 認定調査前の準備 ― 成功のための3つのポイント
認定調査は、自分の状態を正しく伝えることが大切です。
そのためにも、事前にしっかり準備しておくと安心です。
① 事前に質問項目を確認しておく
調査では、調査員が日常生活や身体の状態について詳しく質問してきます。内容は全国共通の調査票に基づいており、およそこのような項目があります。
- 身体の動き(起き上がり・歩行など)
- 食事・排泄・入浴・着替えなどの日常生活動作
- 物忘れや判断力などの認知機能
- 行動面の状態(徘徊・不安・暴言など)
- 医療的ケア(酸素・点滴など)
- 生活の環境や家族状況
事前にどんな質問があるのか分かっているだけで、当日は落ち着いて答えられます。調査項目は市区町村の窓口やインターネットでも確認できます。
② 日頃の状態をメモしておく
認定調査でよく聞かれるのは、「ここ1ヶ月の様子」です。
でも、いきなり聞かれると具体的に思い出すのはなかなか難しいもの。
そこで、日頃から次のようなことをメモしておくのがおすすめです。
- 普段どんなところで困っているか
- できること、できないこと
- 体調の変化
- 病院受診の記録
- 利用しているサービスの内容
ポイントは「できるだけ具体的に書く」こと。
例:
❌ 「歩くのが大変」
⭕ 「10分以上歩くと足が痛くなる」
⭕ 「家の中でも伝い歩きが必要」
このように具体的に記録しておくと、調査員にも状況が正しく伝わりやすくなります。写真や動画で残しておくと、さらに理解してもらいやすいです。
③ 家族やケアマネジャーと情報共有しておく
認定調査は、本人だけでなく周りの協力も大切です。
特に、
- 一人暮らしの方
- 認知症の症状がある方
は、本人だけではうまく説明できないことがあります。
家族やケアマネと日頃から情報を共有し、
「誰がどの情報を伝えるか」
「どんな困りごとがあるのか」
を整理しておきましょう。
ケアマネジャーは介護制度に詳しいので、
- 調査でどんな点が見られやすいか
- 何を伝えるべきか
など、具体的なアドバイスもしてくれます。当日に同席してもらえると、より安心して調査を受けられます。
◆ 認定調査当日に心がけたいこと
調査当日は緊張する方も多いですが、落ち着いて自分の状態を伝えることが大切です。ここでは、当日に気をつけておきたいポイントをまとめました。
① 家族が同席すると安心
認定調査では、できるだけ 家族の同席 をおすすめします。本人だけではうまく説明できないことがあったり、忘れてしまうこともあるため、家族が補足説明をしてくれると調査員により正確に伝わります。
特に、
- 認知症の症状がある方
- 不安が強い方
- 一人暮らしの方
の場合は、家族の存在が大きな支えにもなります。
ただし、家族が話しすぎるのはNG。本人の思いを尊重しつつ、不足部分だけを補う姿勢が大切です。
② “良いところを見せようとしない”ことが大事
認定調査で一番多いミスは、「実際よりも元気に見せようとしてしまう」こと です。
- 手すりがあれば歩けるのに、頑張って手すりなしで歩いてしまう
- 本当は毎日苦労しているのに、「大丈夫です」と言ってしまう
- トイレ介助が必要なのに恥ずかしくて言えない
これは“優しさ”や“見栄”からくる行動ですが、結果として 必要な支援を受けられなくなる可能性 があります。
調査員はできる限り客観的に判断しようとしていますので、そのままの状態を正直に伝える ことが一番大切です。
③ 具体的な例を交えて説明する
調査員に状況が伝わりやすくなるコツは、抽象的な言い方ではなく、具体的なエピソードを話すこと です。
例:
❌ 「物忘れがひどい」
⭕ 「朝飲んだ薬を何度も確認してしまう」
⭕ 「料理の途中で何をしていたか忘れてしまう」
❌ 「歩くのが大変」
⭕ 「家の中でも壁づたいで移動している」
⭕ 「10分歩くと足が痛くなる」
このように“数字”や“具体的な場面”を入れると、調査員もイメージしやすくなります。
◆ 結果に納得できないときの対応
要介護認定は、生活の質を左右する大切な結果です。もし結果に不安や疑問がある場合は、次の方法を検討できます。
① 不服申し立て
認定結果にどうしても納得できない場合、「不服申し立て」ができます。通知を受け取った日の翌日から 3か月以内 に手続きが必要です。
- 市区町村に書面を提出
- 専門家で構成される審査会で再審査
という流れになります。
ただし、手間や時間もかかるため、まずはケアマネジャーに相談するのがおすすめです。
② 区分変更申請
認定後に状態が悪化した場合や、明らかに今の区分が合わない場合、区分変更申請 を行うことで再調査を受けられます。
- 病気やケガでADLが大きく落ちた
- 認知症状が進行した
- 日常生活が急に困難になった
こうしたときは、早めにケアマネジャーや市区町村に相談しましょう。
③ ケアマネジャーへの相談
認定結果に疑問があるとき、頼れるのはやはりケアマネジャーです。
- 結果の妥当性
- 利用できるサービス
- 今後の対策
- 区分変更の必要性
などを客観的にアドバイスしてくれます。また、ケアプランの調整やサービス選びにも大きな力になってくれます。
◆ まとめ ― 認定調査は“未来の生活を守る第一歩”
要介護認定調査は、介護サービスを受けるための大切な入口です。適切な結果を得るためには、次のポイントを押さえておくことが重要です。
- 事前に質問項目を知っておく
- 日頃の状態を具体的にメモしておく
- 家族やケアマネジャーと情報共有
- 当日は“良いところを見せようとしない”
- 具体的な事例で説明する
- 結果に納得できない場合は早めに相談する
認定調査はただの手続きではなく、これからの生活をもっと良くするための重要なステップ です。
「わかってもらえないかもしれない…」
「どう話せばいいのかわからない…」
そんな不安がある方も、しっかり準備すれば大丈夫。
この記事が、あなたの不安を少しでも減らし、より良い介護サービスにつながる手助けになれば幸いです